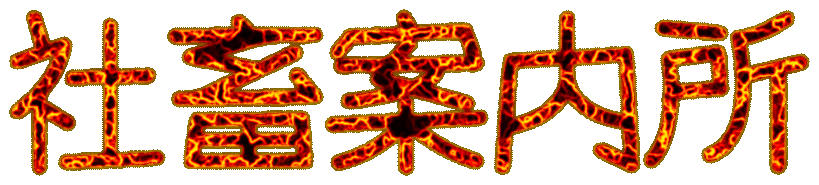会社を運営するにあたり必須の資格というものがいくつかあるが、衛生管理者もそのひとつである。
労働安全衛生法で定められた国家資格であり、従業員が50人以上の事業所単位で必須となるため、相当需要が高いので持っていると重宝される。
合格率は45%程度のようで、それほど難しいことはないのであるが、なめてかかると痛い目にあう。
攻略法としては、過去問のパターン分析と出題の要点を抑えることにつきる。
講座も開催されているのだが、これはお勧めしない。
正直言って講義を聴いていても効率が悪く、ただただ眠いだけで費用の無駄になる。
(私も参加したのだが、ほとんど寝ていた)
過去問について注意したい点は、ただ暗記しただけでは危険ということである。
全く同じ問題が出題されることはまれで、問題文中の一部を変えてひっかけてくることが多いため、回答を暗記しただけではまんまとひっかかるのである。
そのため、各出題ポイントの要点を押さえておく必要がある。
この要点を集中的に覚えていくことが最も効率的な攻略法である。
過去問と解説についてはネットで公開されているので、これを活用したい。書籍も2000円程度で入手できて有効である。

では具体的な手順を説明する。
- その1
- 出題のパターンをリストにして、必ず出題される分野、高確率で出題される分野、たまに出題される分野の3パターンに分類する。
- その2
- 必ず出題される分野と高確率で出題される分野の要点を書きだして覚える。
- その3
- たまに出題される分野は、問題文+回答のパターンを丸暗記する。余裕があれば要点を書きだして覚える。
特に1題目にでてくる衛生管理者の選任に関する出題は必ずでるのだが、これが厄介なことに一番複雑でひっかけやすい出題となっている。
必ずでるので確実に点数を稼ぎたいところではあるのだが、苦手な人はあえて覚えず捨てに行く戦法もありかと思う。
以下に私が使用した要点ノートである。
一度勉強してみたかたなら何となく理解できると思うので参考にしていただきたい。◎が必須分野、○が高確率分野である。
◎衛生管理体制
- 製造業300人以上は統括安全衛生管理者
- 800人は衛生管理者3人必要、有害業務に30人以上は専任の衛生管理者、(低温、振動、騒音を除いて)衛生工学衛生管理者
- 産業医は50以上
- 有害、深夜に500人以上は専属の産業医、3000人は2人以上、月1回巡視
- 50人以上は衛生委員会、毎月1回以上、長時間労働の対策も含まれる
- 医師による面接指導: 週40時間、月100時間以上、労働者の申請による、遅延無く必要な措置をとる
○設備の定期点検
- 全体換気装置は定期点検の対象外、対象は局所排気、プッシュプル、除じん、排ガス、排液装置
- アンモニア、塩酸、一酸化炭素は第3類で、排ガス、排液対象外
機械の譲渡、設置
- 該当: 防塵、防毒、再圧、潜水、ガンマ線、チェーンソー
- 該当外: 防音、化学防護、防振
作業環境測定
- 測定士が測定を行う作業場: 粉じん、化学物質、石綿、有機溶剤
- 測定頻度: 騒音→6か月、暑熱寒冷、坑内→半月、放射線→1ヶ月
- 測定対象外: 硝酸、アンモニア、フェノール
健康診断
- 項目: 高圧→四肢の運動・肺活量、黄りん・酸類→歯、放射線→皮膚
- 血圧、自覚症状は省略できない、3か月以内、50人以上は報告だが雇用時の報告は必要ない
作業主任者
- 必要: 酸素欠乏場所(酒類のタンク、サイロ、ドライアイス)、放射線、鉛、有機溶剤、高圧、石綿
- 必要ない: 粉じん、レーザー、超音波、騒音、潜水、はんだ付け、研究業務
特別教育
- 必要: チェーンソー、高圧、酸欠、エックス線、ガンマ線、特定粉じん、焼却、石綿
- 必要ない: 超音波、潜水、有機溶剤、騒音、紫外線、赤外線
健康管理手帳
- 対象: 石綿、塵肺管理区分2以上、塩化ビニル、ジアニシジン、ベリリウム、ベンジジン、ベーターナフチルアミン
- 対象外: 水銀、シアン化水素、ベンゼン、鉛、硝酸、塵肺管理区分1
衛生基準
- 立ち入り禁止区域: 炭素濃度1.5%以上、酸素濃度18%未満、硫化水素100万分の10以上、暑熱寒冷
- 騒音、ダイオキシンは6か月に1度測定する
◎有機溶剤
- 5%以上、 局所排気またはプッシュプル排気装置を設ける、点検・健康診断は6か月以内
- 囲いフード0.4、1種→赤、2種→黄色、3種→青
◎特定化学物質
- 禁止: ベンジジン 許可必要: ベリリウム、ベンゾトリクロリド、ジアニシジン、アルファーナフチルアミン
- 廃業時に提出: 作業環境測定、従事期間、健康診断票
○酸素欠乏症
- 第1種→酸素、第2種→硫化水素(100万分の10)、防毒マスクは不可
粉じん
- 特定粉じん作業: セメント、フライアッシュ、手持ち工具以外の研磨 →局所排気、年1点検
- 測定6か月ごと、毎日清掃
放射線
- 管理区域: 3か月1.3mSv、10分の1超える恐れ、1㎝線量
- 被爆限度: 5年100mSv、かつ1年50mSv、妊娠は3か月5mSv
◎有害物質
- ガス: 塩素、臭化メチル
- 蒸気: アセトン、硫酸ジメチル、トリクロルエチレン、ニッケルカルボニル
- 粉じん: ジクロルベンジジン
- ミスト: 液体の微細な粒子が浮遊、
- ヒューム: 金属の微粒子が浮遊
◎化学物質による健康障害
- 一酸化炭素: 息切れ、意識障害
- シアン化水素: 呼吸困難、痙攣
- 弗化水素: 粘膜刺激、骨の硬化、斑状歯
- 二酸化窒素: 歯牙酸蝕症、胃腸障害
- 酢酸メチル: 視覚障害
- 二酸化硫黄: 気管支炎、歯牙酸
- ベンゼン: 貧血、白血病
- メタノール: 視神経障害
- 二硫化炭素: 精神障害
- 生物学的半減期: 体内に取り込まれた有害物質が代謝排出され半分になるまでの期間
金属障害
- 鉛: 貧血、神経障害、腹部の疝痛
- マンガン: パーキンソン病
- 水銀: 精神障害、手指の震え
○有機溶剤障害
- 有機溶剤: 空気より重い、脳に入りやすい、呼吸器と皮膚から吸収される
- 黒皮症はヒ素、メタノール・酢酸メチルは視神経、ノルマルヘキサンは神経炎、二硫化炭素は精神障害、トリクロロエチレンは肝障害
熱中症
- 熱痙攣: 多量に発汗後水分のみ補給されたとき
- 熱射病: 体温の上昇、発汗の停止、重篤な症状
○騒音
- 騒音性難聴: 内耳の蝸牛の有毛細胞の変化、4000ヘルツ付近が低下、C5dip
- 騒音レベル: A特性、等価騒音レベル: 変動する騒音の平均値で人間の心理生理反応とよく対応する
○有害光線
- 波長短い: X線、紫外線
- 長い: マイクロ波、赤外線
◎排気
- 空気清浄装置は排風機の前
作業環境測定
- A測定: 平均
- B測定: 発散源から近い場所
- 第3管理区分: B測定1.5倍、A測定第2評価値が管理濃度こえ
◎排気装置
- 囲い式(ドラフトチェンバー)>外付け式(グリッド)>レシーバー式(キャノピー) 側方・下方>上方
◎保護具
- 一酸化炭素: 赤
- 有機ガス: 黒
- 高濃度有害ガスに対しては送気マスクか自給式呼吸式
- 防毒マスクは耳にかけない
- 強烈な騒音には耳栓と耳覆い併用
- 複数のガスが混在しているときは送気マスク
○特殊健康診断
- 有機溶剤の生物学的半減期は短いので、有機溶剤代謝物の検査は検尿の時刻を管理する必要がある
◎事業場の施設
- 50人又は女性30人は男女別の休憩所、大掃除は6か月、炊事専用の便所と休憩所、換気は床面積1/20以上
変形労働時間
- 妊産婦が請求した場合は残業不可、監督署に届けなければならない
- 8時間以上は1時間、6時間以上は45分の休憩 機密事務には適用されない、フレックスタイムの清算は1ヶ月
就業規則
- 安全・衛生は定めなくてもよい、変更は代表者の意見を聞く必要がある、周知は電子媒体でもよい
有給休暇
- 4年16日、5年18日、6年20日 時効は2年 機密事務にも適用される
- 産休は6・14・8、 休業後30日は解雇不可
- 妊産婦はフレックス可、深夜業は不可
温度
- 温熱環境は、気温、湿度、気流、放射熱からなる 至適温度は熱からず寒からず、人によって異なる
事務室換気
- 必要換気量= 在室者のCO2/室内基準濃度―外気濃度
○食中毒
- ノロウイルスは冬季、石鹸きかない、潜伏1~2日
- サルモネラは感染型、黄色ブドウは毒素型、腸炎ビブリオは感染型好塩菌
○労働衛生管理
- 病休度数=件数/時間
- 病休強度=日数/時間
- 疾病休業日数=日数/日数
- 疾病件数年千人=件数/労働者数
心の健康の保持促進
- 衛生委員会によるケアは該当しない
- 情報取得は本人の同意が必要
○VDT作業
- 連続作業は1時間以内、休憩10~15分、
- 書類上は300ルクス以上、画面上は500ルクス以下、
- 画面の距離は40センチ以上
○喫煙
- 出来るだけ屋外に排出、
- 空気清浄器に有害ガスは除去できない、
- 密閉してはいけない、風は0.2m/S以上
◎一次救命処置
- 顎を上げる、判断は10秒観察、圧迫30回に呼吸2回、5センチ沈む強さで1分間に100回
止血
- 直接法で行う、間接は心臓に近い部位、止血帯の帯は幅3センチ以上、出血1/3以上は危険
○火傷
- Ⅱ度~水泡、Ⅲ度~ただれ、ショック時は水平にして足を上げる、冷やすときは低体温に注意
骨折
- 複雑は開放骨折、ヒビは不完全骨折、
- 副子は長いものを使用、脊髄損傷は硬い板に載せて搬送する
○脳血管障害
- 脳血栓~脳血管自体、脳塞栓~心臓や動脈の血栓による、門脈は消化管
◎血液
- グロブリンは免疫、凝固はフィブリノーゲンがフィブリンに変化、抗体を生産するのはBリンパ球、赤血球の寿命120日
◎心臓
- 左心室から出て右心房に戻る、肺動脈は酸素少ない
◎呼吸
- 横隔膜による、呼吸中枢は延髄にある、肺のガス交換は外呼吸
消化吸収
- タンパク質~トリプシン、ペプシン ビタミンアミノ酸はそのまま吸収される
肝臓
- 脂肪酸の分解、血漿タンパクの合成、ブドウ糖の合成、グリコーゲンの合成、有害物質の分解、胆汁の分泌血液凝固物質の合成
○代謝
- エネルギー発生~異化、合成~同化、基礎代謝量は体表面積に比例、タンパク質はトリプシノーゲン、ヘリパーゼは脂肪
体温調節
- 中枢は間脳の視床下部、寒冷時は血管収縮、高温時は血管拡張、1日850g蒸発
○腎臓、尿
- 尿は弱酸性、腎機能低下すると尿素窒素が増加、糸球体は血球とタンパク質以外をろ過、尿細管で糖アミノ酸等を再吸収
○筋肉
- 酸素の供給が不十分だと乳酸に分解、等尺性~姿勢維持、等張性~運動、収縮する瞬間が最も強い、繊維の太さに比例
◎神経系
- 消化管の促進は副交感神経、自律神経の中枢は脳幹(視床下部)と脊髄、内蔵血管などの不随意筋に分布、外側皮質が感覚中枢
○感覚
- 痛覚が大きい、温覚より冷覚が鋭い、色は錐状体、明暗は杆状体、前方は近視、後方は遠視、光量を調節するのは虹彩
- 内耳は前庭と半規管(平衡感覚)と蝸牛(聴覚)からなる、
○BMI
- 体重/身長×身長(m)
ホルモン
- コルチゾール:副腎皮質、
- メラトニン:松果体、
- アドレナリン:副腎髄質、
- パラソルモン:副甲状腺、
- アルドステロン:副腎皮質